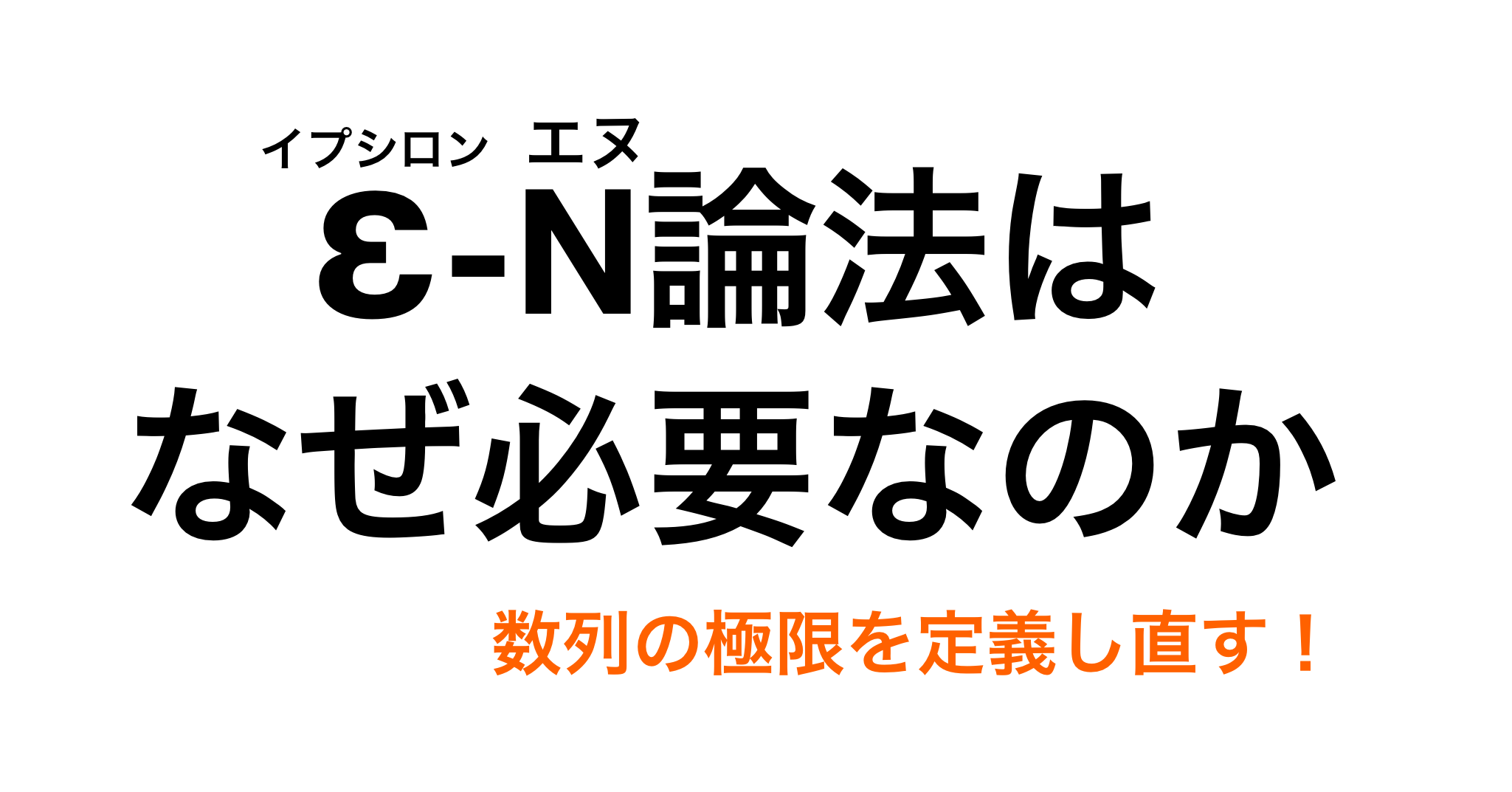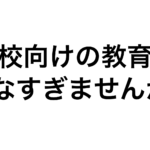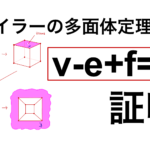今回の内容の動画版はこちら→解析学の基礎01 イプシロン-エヌ論法はなぜ必要か
大学の解析学では\( \varepsilon-\delta \)(イプシロン-デルタ)論法とか\( \varepsilon-N \)(イプシロン-エヌ)論法とかいう手法ををつかいます。これは高校の直感的な極限の定義を改め、厳密な議論ができるようにした方法です。
高校の数学3の教科書には以下のような”直感的な”数列の極限の定義が書いてあります。
数列\( \{a_n\} \)において、\( n \)を限りなく大きくするとき、\( a_n \)が一定の値\( \alpha \)に限りなく近づくならば、これを
「\(\displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n=\alpha \)」 または 「\( n\to\infty \)のとき\( a_n\to \alpha \)」
のように表し、この値\( \alpha \)を数列\( \{a_n\}\)の極限値という。また、このとき数列\( \{a_n\}\)は\( \alpha \) に収束するといい、数列\( \{a_n\}\)の極限は\( \alpha \)であるともいう。
これに対し、大学での数列の極限の定義は次のようになります。これが\( \varepsilon-N \)(イプシロン-エヌ)論法と呼ばれるものです。
\( n>N \)となるすべての\( n \)について\( |a_n-\alpha|<\varepsilon \)
となるならば、これを
「\(\displaystyle \lim_{n\to\infty}a_n=\alpha \)」 または 「\( n\to\infty \)のとき\( a_n\to \alpha \)」
のように表し、この値\( \alpha \)を数列\( \{a_n\}\)の極限値という。また、このとき数列\( \{a_n\}\)は\( \alpha \) に収束するといい、数列\( \{a_n\}\)の極限は\( \alpha \)であるともいう。
大学の定義では「限りなく大きく」という言葉が排除されています。また、任意の\( \varepsilon \)に対して…と宣言した後はこの\( \varepsilon \)は(\( 0.1 \)とか\( 0.05 \)のような)定まったただの数として扱います。\( 0 \)にどんどん近づける…みたいなことはしなくていいのです。このようなことから、高校の定義は”動的”、大学の定義は”静的”な感じと言われることもあるようです(私も個人的に”静的”な感じという表現がとてもよく合っているように感じます)。
さて、厳密に議論ができるようになるとはいっても、高校生目線でいうとなぜそんなめんどくさいのを導入するんだという気持ちになるのは自然のことです。なぜイプシロン-エヌ論法なるものを導入するのでしょうか。それは、収束の定義を高校範囲のままにしておくと収束の証明が難しかったり、曖昧になるような例がたくさんあるからです。ということで次の例を考えてみましょう。
数列\( \{a_n\} \)が\( a_n\to 0 (n\to\infty)\) ならば
\( \displaystyle \frac{a_1+a_2+\cdots +a_n}{n}\to 0 (n\to \infty) \)
であることを示せ。
(証明の前に)
\( \varepsilon-N \)論法に興味を持った方は、まず上の証明を高校の極限の定義でやれるか試してみると良いでしょう。
念のため確認しておきますが、次のような計算は誤りです。
(誤り1) \( \displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots +a_n}{n}\)
\( \displaystyle \ \ =\lim_{n\to \infty}\frac{0+0+\cdots +0}{n}=0 \)
(誤り2)\( \displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots +a_n}{n}\)
\( \displaystyle \ \ =\lim_{n\to \infty}\frac{a_1}{n}+\lim_{n\to \infty}\frac{a_2}{n}+\cdots\lim_{n\to \infty}\frac{a_n}{n}\)
\( \ \ =0+0+\cdots +0=0 \)
(誤り1)は気持ちは分かりますが、\( a_1, a_2, a_3 \)などは定まった値ですから極限をとっても値は変化しませんし、そもそも分子と分母で極限を”時間差”でとろうとしているのもダメです。また、(誤り2)のように和がどんどん増えていく極限に対してむやみに\( \lim \)を分ける計算をしていけないのは、連続関数に対する区分求積法
\( \ \ \displaystyle \small \int_0^1f(x)dx \)
\( \displaystyle \small=\lim_{n\to \infty}\left\{\frac{1}{n}f\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots \frac{1}{n}f\left(\frac{n}{n}\right)\right\} \)
の計算からも分かります。もし\( \lim \)を分けて良いならば\( f \)に関係なく、右辺の値はいつでも\( 0 \)となってしまいます。このように、高校範囲の極限の定義のままだとゼロに収束することを示すのはかなり困難なのです(もし、高校範囲でできる方法を知っている方がいれば是非教えてください…)。
では、問1の証明をイプシロンエヌ論法で示してみましょう。
数列\( \{a_n\} \)が\( a_n\to 0 (n\to\infty)\) ならば
\( \displaystyle \frac{a_1+a_2+\cdots +a_n}{n}\to 0 (n\to \infty) \)
であることを示せ。
(問1の証明)
まず任意の正数\( \varepsilon \)を一つ定める。これは議論の中では動くことのない定数である。
仮定より\( a_n\to 0 \)であるから、任意の正数\( \varepsilon’ \)(これは今のところ上の\( \varepsilon \)とは独立に定めた別モノと考えてよい)に対して適当な番号\( N_1 \)を定めると、\( n>N_1 \)となるすべての番号で\( |a_n-0|<\varepsilon’ \)が成り立つ。ここで、\( n>N_1 \)の任意の\( n \)について、
\( \displaystyle \frac{a_1+a_2+\cdots a_n}{n} \)
の分子を\( a_1 \)から\( a_{N_1} \)までと、\( a_{N_1+1}\)から\( a_n \)までに分けて、三角不等式(\( |A+B|\leq |A|+|B| \))を繰り返し使うと、次の①を得る。
\( \displaystyle \small \left|\frac{a_1+a_2+\cdots +a_n}{n}\right| \)
\( \displaystyle \scriptsize \leq \left|\frac{a_1+a_2+\cdots +a_{N_1}}{n}\right| +\frac{\left|a_{N_1+1}\right|+\left|a_{N_1+2}\right|+\cdots +\left|a_n\right| }{n} \) …①
ここで\( |a_{N_1}|, |a_{N_1+1}|, \cdots |a_{n}|\)らはすべて\( \varepsilon’\)より小さいから、①の第二項は\( n>N_1 \)となる任意の\( n \)で
\( \displaystyle \frac{\left|a_{N_1+1}\right|+\left|a_{N_1+2} \right|+\cdots +\left|a_n\right| }{n}\)
\( \displaystyle \small < \frac{\varepsilon’+\varepsilon’+\cdots+\varepsilon’}{n}=\frac{(n-N_1)\varepsilon’}{n} < \varepsilon’ \) …②
となる。また、\( |a_1+\cdots +a_{N_1}| \)は定まった(\( n \)と関係のない)ただの定数であるから、ある番号\( N_2 \)があって、\( n>N_2 \)となる任意の\( n \)で
\( \displaystyle \ \ \frac{ |a_1+\cdots +a_{N_1}| }{n}<\varepsilon’ \) …③
が成り立つ。
以上のことから、\( N_1, N_2 \)のうち、大きい方を\( N \)とおくと、\( n>N \)となる任意の\( n \)で②および③が成り立つ。すなわち、①において\( n>N\)となる任意の\( n \)で
\( \displaystyle \ \ \frac{ |a_1+\cdots +a_{n}| }{n}<2\varepsilon’ \)
となる。さて、いま議論のはじめに固定していた\( \varepsilon \)と\( \varepsilon’ \)は直接関係していない値であったが、ここで\( 2\varepsilon’=\varepsilon \)となるように、すなわち\( \varepsilon’ \)を\( \varepsilon \)の\( \frac12 \)として定めることにしよう。(\( \varepsilon’ \)は任意のものとしてきたのだから大きさをこのように定めても問題はない)
そうすると\( n>N\)となる任意の\( n \)で
\( \displaystyle \ \ \frac{ |a_1+\cdots +a_{n}| }{n}<\varepsilon \)
が成立することになる。これは\( \frac{ a_1+\cdots +a_{n} }{n}\to 0\)を意味する。(証明終)
証明の中ではどんどん近づくとかいった表現はなく、\( \varepsilon \)を定数と固定していたり、番号\( N_1, N_2 \)についても宣言以降は動くことのない定まった番号として扱っています。このあたりが”静的”な感じと言われる所以なのだと思います。
今回は数列の極限に関する\( \varepsilon-N \)論法のみ扱いました。これの関数版が\( \varepsilon-\delta \)論法となりますが、思想的にはほぼ同じものです。\( \varepsilon-N \)論法の理解が十分になれば自然と\( \varepsilon-\delta \)論法も自力で扱うことができるようになるでしょう。\( \varepsilon-\delta \)論法についてはまたどっかで扱うかもしれません。
では今回はこの辺で。
(参考文献)
★★★
今回の内容とほぼ同じことを話した動画です。